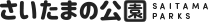新しい解説ラベルをつくりました
小髙
2022年2月28日
園内で,よく聞こえてくる疑問の1つに「アカハナグマってなに?」があります。あまりなじみのない動物なので、まずどの動物の仲間なのかわかりません。名前を見ても、カタカナではどこで区切るのかもわかりません。目の前にいるのは、細長くとがった顔で長い尾を持った茶色い動物です。小獣舎と呼ばれる小型肉食・雑食獣を集めた獣舎で飼育しており、昼行性なので開園直後や午後3時前後に活動している姿をよく見ることができます。隣にいるのはニホンアナグマでこちらも何の仲間かわかりづらい動物です。どちらにも「クマ」が付きますが、どちらも「クマ」ではありません。漢字で書くとすれば、穴熊、赤鼻熊でしょう。漢字になってもどこに区切りがあるのかは不明です。しかし、英語で表すとよくわかります。よく知られる「クマ」はbearです。アナグマはbadger、そしてアカハナグマが含まれるハナグマはcoatiです。もし、名前が英語で書かれていたら、アカハナグマをクマの仲間だと思う人はいないでしょう。「アカハナグマ」は、食肉目(ここまではクマもアナグマも同じです)アライグマ科(ここで他と分かれます)のハナグマ属のなかで、体の色が赤茶色いハナグマのことです。名前1つで色々なことがわかりますね。


現在、動物の種類は約140万種、そのうち哺乳類は約5500種です。動物には国際的な基準で科学的な名称がつけられていて(「学名」といいます)、ラテン語かラテン語化した名詞と形容詞で表します。しかし、日本では発音しやすく意味が分かりやすい「和名」を使います。漢字を使用すると意味が分かりやすくなりますが、動物園では種の名前はカタカナで表記することになっています。知らない動物を見たとき、私たちはまず動物の名前や分類・分布の書かれた看板(種別ラベルといいます)を見ます。カタカナで書かれた動物の名前を読んだだけではわからない時は、ぜひそこに書いてある英名や学名にも目を向けてください。そして想像してみてください。なぜそんな名前がついたのか。和名でも英名でも同じポイントに注目して付けられた名前もあれば、全く別のところで区別している名前もあります。結局、疑問は尽きないのかもしれません。



動物園では、生きている生物(動物、昆虫、植物等)を見て楽しむだけではなく、その生物が生きている環境や生物同士の関係などいろいろなことを知ることができます。そのお手伝いをするために私たちは解説板を作っています。工具で材木を切り、塗料を塗り、イラストを描き、PCで文章を書き設置する。ヒトが生きてゆくために必要な知識ではないかもしれませんが、知っていると生活が豊かになる雑学。新たなことを知るためのきっかけとなる豆知識。動物園で増やしてみてはいかがでしょうか?